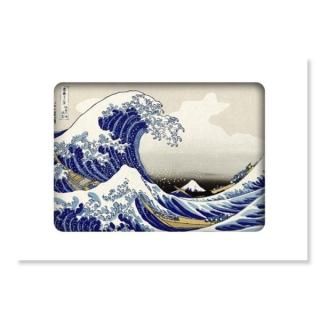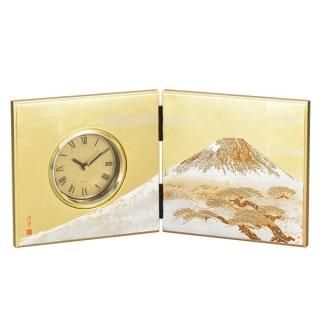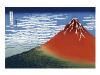外国人が喜ぶ日本のおみやげ・贈り物専門店
コラム
インバウンド需要に対応できる商品を開発するポイント

円安や水際対策の大幅な緩和を背景に、
日本のインバウンド市場は今、かつてないほどの熱気に包まれています。
街には多種多様な言語が飛び交い、観光地や商業施設は連日多くの訪日外国人観光客で賑わいを見せています。
この巨大な消費パワーを、自社の成長に繋げたいと考える事業者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした課題意識を持つ企業の経営者、そしてマーケティングや商品開発の担当者の皆様のために、インバウンド需要の本質を解き明かし、これからの時代に選ばれる商品を開発するための具体的なポイントを、最新のデータやトレンドを交えながら体系的に解説していきます。
インバウンド需要とは
インバウンド(inbound)とは、元々「内向きの、入ってくる」といった意味を持つ英語ですが、旅行・観光業界においては、外国人が日本へやってくる旅行のことを指します。
これに対し、日本人が海外へ出かける旅行は「アウトバウンド(outbound)」と呼ばれます。
したがって、「インバウンド需要」とは、日本を訪れる外国人観光客(訪日客)によって生み出される、宿泊、飲食、交通、そして商品購入といった、様々な領域における消費ニーズの総体を意味します。
単に「お土産が売れる」といった狭い意味ではなく、彼らが日本に滞在中に求めるあらゆるサービスや体験、そして商品に対する巨大な市場、それがインバウンド需要の本質です。
この市場を理解し、的確に応えていくことが、これからの日本経済、そして各企業の成長において極めて重要な鍵を握っています。
インバウンド需要が注目される理由
なぜ今、これほどまでにインバウンド需要が注目を集めているのでしょうか。
その背景には、経済的な要因と、国策としての強力な後押しがあります。
経済の活性化が見込まれるため
観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によると、2024年1-3月期の訪日外国人旅行消費額は、四半期ベースで過去最高となる1兆7,505億円に達しました。
これは、コロナ禍前の2019年同期と比較しても50%以上高い水準であり、その成長ポテンシャルは計り知れません。
この消費は、宿泊業や飲食業、運輸業といった観光関連産業に直接的な恩恵をもたらすだけでなく、そこで働く人々の所得を増やし、さらには土産物として購入される農産品や工芸品、化粧品、医薬品といった、地方の製造業や小売業にまで、その波及効果が及びます。
少子高齢化による国内市場の縮小が懸念される中、この旺盛な「外需」を取り込むことは、日本経済全体の活性化、特に地方創生において、極めて重要な成長エンジンとなっているのです。
政府が観光産業の成長を推進しているため
インバウンド需要の拡大は、国を挙げた一大プロジェクトでもあります。
日本政府は、「観光立国」の実現を成長戦略の重要な柱と位置づけ、具体的な数値目標を掲げて様々な施策を推進しています。
2023年3月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」では、
- 2025年までに、訪日外国人旅行者数をコロナ禍前の水準(2019年:3,188万人)を超えるレベルまで回復させる
- 訪日外国人旅行消費額5兆円の早期達成を目指す
- 将来的には「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の3つを柱に、質の高いインバウンド市場を形成する
ビザの発給要件の緩和や、空港・港湾の整備、そして地方の観光資源の磨き上げなど、官民を挙げた取り組みが今後も継続的に行われることから、インバウンド市場は長期的に安定した成長が見込まれる、非常に魅力的なマーケットであるといえます。

インバウンド需要に対応するメリット
企業がインバウンド需要に積極的に対応することは、単に新たな顧客層を獲得するというだけに留まらず、会社経営そのものに多くのポジティブな影響をもたらします。
メリット①売上高と利益率が向上する
最大のメリットは、もちろん売上と利益の向上です。
国内需要だけをターゲットにしていた事業者がインバウンド需要を取り込むことで、新たな顧客層を開拓し、売上の絶対額を大きく伸ばすことが可能になります。
また、訪日外国人観光客は、旅行という非日常的な高揚感から、財布の紐が緩む傾向にあります。
特に、「Made in Japan」の高品質な商品や、そこでしか手に入らない限定品に対しては、価格が高くても購入を厭わないケースが多く見られます。
付加価値の高い商品を開発し、適正な価格で提供することで、利益率の向上も期待できるのです。
メリット②店舗オペレーションが高度化する
インバウンド対応を進める過程は、自社の店舗運営や業務プロセスを見直し、高度化させる絶好の機会となります。
- 多言語対応: 商品説明やメニュー、Webサイトなどを多言語化する過程で、情報伝達のあり方が洗練されます。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進: 多様なキャッシュレス決済への対応や、免税手続きの電子化、SNSでの情報発信などを進めることで、店舗全体のデジタル化が加速します。
- 従業員のスキルアップ: 外国語での接客や、異文化への理解が深まることで、従業員の対応スキルが向上します。
これらの取り組みは、結果的に日本人のお客様に対するサービスの質の向上にも繋がり、店舗全体の競争力を高めることに貢献します。
メリット③地域経済と連携した長期的な成長ができる
インバウンド対応は、一企業だけで完結するものではありません。
地域の他の事業者や、観光協会、自治体などと連携することで、より大きな価値を生み出すことができます。
例えば、地域の農家と連携して特産品を使った新商品を開発したり、近隣の宿泊施設や交通機関と連携して周遊パスを企画したりすることで、「点」であった個々の事業者が「面」となり、地域全体で旅行者を呼び込み、滞在時間を延ばすことが可能になります。
こうした地域連携は、新たなビジネスチャンスを創出するだけでなく、自社がその地域にとってなくてはならない存在となるための、長期的な成長基盤を築くことにも繋がるのです。
小売業に求められるインバウンド対策

魅力的な商品を開発するだけでなく、訪日外国人観光客がストレスなく、快適に買い物を楽しめる環境を整える「受け入れ態勢の整備」も、インバウンド戦略の重要な両輪です。
多言語への対応
言語の壁は、購買意欲を削ぐ最大の要因の一つです。
- 店頭POP・商品説明: 英語はもちろんのこと、東アジアからの観光客が多いことを考慮し、中国語(簡体字・繁体字)や韓国語での表記は必須といえます。商品の特徴や使い方、アレルギー情報などを、ピクトグラム(絵文字)も交えて分かりやすく表示しましょう。
- 接客対応: 全てのスタッフが外国語を話せる必要はありません。翻訳アプリ(ポケトークなど)を導入したり、指差しで会話ができるコミュニケーションボードを用意したりするだけでも、コミュニケーションは格段にスムーズになります。
決済システムの整備と免税対応
快適な決済体験は、顧客満足度に直結します。
- キャッシュレス決済の多様化: 現金を持たない旅行者は年々増加しています。クレジットカードはもちろんのこと、中国で主流の「Alipay」「WeChat Pay」や、東南アジアで普及しているQRコード決済など、多様な決済手段を導入することが求められます。
- 免税(Tax-Free)対応: 免税販売は、インバウンド客にとって大きな魅力です。免税店の許可を取得し、手続きをスムーズに行える体制を整えることは、競合に対する大きなアドバンテージとなります。近年では、手続きを大幅に簡略化できる電子化システムの導入も進んでいます。
Webサイト・SNSを活用した情報発信
多くの旅行者は、訪日前にインターネットで情報を収集します。
旅前の段階で、いかに自社の存在を知ってもらうかが重要です。
- Webサイトの多言語化: 自社の公式ウェブサイトを多言語化し、海外の検索エンジンでも見つけてもらえるように対策(SEO)を施します。
- SNSの戦略的活用: ターゲットとする国・地域で人気のSNSプラットフォームを活用します。例えば、欧米豪向けにはInstagramやTikTok、中華圏向けにはWeibo(微博)や小紅書(RED)などが有効です。魅力的な写真や動画で、商品の世界観や日本の文化を発信しましょう。
地域連携と体験型サービスの提供
前述の通り、近年のトレンドは「コト消費」です。
商品販売と連携した体験型サービスを提供することで、顧客単価と満足度を向上させることができます。
- 体験ワークショップの開催: 和菓子作り体験、伝統工芸の絵付け体験、利き酒体験などを店内で開催し、その体験と関連商品をセットで提供します。
- 観光案内機能の提供: 店舗周辺の観光スポットや、おすすめのレストランなどを紹介するマップを作成・配布するなど、地域のコンシェルジュとしての役割を担うことで、店舗への来訪動機を高めます。
インバウンド向けの商品を開発するポイント

受け入れ態勢の整備と並行して、インバウンド客の心を掴む商品そのものを開発していく必要があります。
ここでは、そのための5つの重要な視点をご紹介します。
日本独自の商品価値の再発見と発信
まずは、自社の商品や地域に眠る資産の中から、「日本ならではの価値」を再発見することから始めましょう。
商品には、その背景にある歴史や開発者の想い、製造工程における細かなこだわり、さらには素材の産地といった、数多くの「物語」が存在します。
これらの物語を掘り起こし、多言語で発信していくことが、ストーリーテリングの第一歩です。
単なるスペックや価格だけではなく、物語を伝えることで、商品に対する共感や愛着が生まれ、価格以上の価値を感じてもらうことができます。
また、伝統的なデザインや技術も、現代のライフスタイルや感性に合わせて再解釈することで、新たな魅力を引き出すことができます。
たとえば、伝統的な着物の柄を取り入れたモダンなエコバッグやスマートフォンケースのように、古き良き要素を現代のプロダクトに落とし込むことで、国内外の新たなファンを獲得できるでしょう。
国ごとのニーズに対応した商品カスタマイズ
ターゲットとする国や地域の文化や嗜好、ライフスタイルに合わせて、商品を柔軟にカスタマイズすることは、ヒット商品の可能性を大きく高めるうえで非常に重要です。
たとえば味覚においては、同じ抹茶味のお菓子であっても、アジア市場では甘みを強めに仕上げ、欧米市場では甘さを控えめにして抹茶本来の苦みを際立たせるなど、地域ごとの好みに応じた調整が効果的です。
また、パッケージデザインにおいても、文化的な意味合いを踏まえた工夫が求められます。
中華圏では赤や金が縁起の良い色とされているため、それらを積極的に取り入れたり、現地の言語で親しみやすいキャッチコピーを添えたりすることで、より現地の消費者に響く商品に仕上がります。
さらに、アパレル商品などでは、体格差を考慮したサイズ展開も欠かせません。
欧米市場向けには大きめのサイズを、アジア市場向けには比較的コンパクトなサイズを用意することで、顧客満足度の向上につながります。
こうした細やかなローカライズの積み重ねが、グローバル市場での成功を支える鍵となります。
参考記事:海外出張でおすすめの手土産10選!選び方のポイントを解説
体験型商品の開発とサービス連携
「モノ」と「コト」を融合させた新たな商品開発が、これからの時代には求められています。
たとえば、工場見学や収穫体験、調理体験といった「体験」を提供し、その場でしか手に入らない限定のお土産とセットで販売することで、訪れた人に特別な思い出と商品を同時に届けることができます。
体験を通じて得られる感動は、商品の魅力や価値を何倍にも高める効果があります。
また、商品単体ではなく、サービスとの連携によって価値を拡張することも有効です。
たとえば、商品を購入した人に、近隣のレストランで使える割引クーポンを配布したり、着物レンタル店と連携して、着物姿で街を散策しながら自社の商品を楽しめるプランを企画したりすることで、体験と商品を一体化させた魅力的な提案が可能になります。
効果的な商品陳列と店舗レイアウト
店舗での商品の見せ方は、売上に大きな影響を与える重要な要素です。
たとえば、もっとも商品を手に取りやすいとされる目線の高さ、つまり床から75cm〜135cm程度の「ゴールデンゾーン」を活用し、特に売りたい商品をこの高さに集中的に陳列することで、購買率の向上が期待できます。
また、「お土産におすすめ」「抹茶特集」「Made in Japan雑貨」など、テーマを設定して関連商品をひとまとめに陳列することで、来店者が目的の商品を見つけやすくなり、滞在時間の延長や複数点購入の促進にもつながります。
さらに、店内の通路幅や動線に配慮し、自然と隅々まで歩き回りたくなるようなレイアウトを設計することも大切です。
こうした回遊性の高い売場づくりは、お客様の視線や関心を引きやすくし、思いがけない商品の発見や衝動買いを誘発します。
リピート購買を促す戦略的商品展開
一度の購入で終わりにせず、帰国後も継続的に顧客であり続けてもらうためには、購入後のフォローと関係構築の戦略が欠かせません。
たとえば、商品パッケージや店舗内に越境ECサイトのQRコードを掲示し、帰国後もオンラインで簡単に再購入できることを明確に伝えることで、リピート購入につなげることができます。
現地での感動や満足が冷めないうちに、「また買える」「いつでも手に入る」と感じさせる導線づくりが重要です。
さらに、日本茶や調味料、お菓子など、日常的に消費される商品に関しては、海外発送に対応したサブスクリプションモデルを導入することで、定期的な購買を促進できます。
こうしたサービスは、利便性の高さに加え、日本とのつながりを感じ続けられる仕組みとしても機能します。
加えて、SNSを活用した継続的な関係構築も欠かせません。
公式アカウントをフォローしてもらい、新商品の情報や季節の話題、日本文化にまつわる投稿を発信し続けることで、ブランドへの関心を維持し、ファンとしてのつながりを深めることができます。
インバウンド需要に対する課題

活況を呈するインバウンド市場ですが、その裏側では、いくつかの社会的な課題も顕在化しています。
事業者として、これらの課題にも目を向け、持続可能な観光の一翼を担う意識を持つことが求められます。
オーバーツーリズム
特定の観光地に、キャパシティを超える数の観光客が集中することで、交通機関の混雑、ゴミ問題、騒音、そして地域住民の生活環境の悪化といった問題が発生します。
これが「オーバーツーリズム(観光公害)」です。
これに対し、事業者は、早朝や夜間といった時間帯に楽しめる体験サービスを開発して訪問時間を分散させたり、まだあまり知られていない地域の魅力を発信して、観光客を新たな場所へ誘導したり、といった貢献が考えられます。
二次交通
主要な空港や駅から、地方の観光地へと向かうためのバスや鉄道といった「二次交通」の利便性が低いことも、地方誘客の大きな課題となっています。
多言語対応の不足や、便数の少なさ、分かりにくい乗り換えなどが、旅行者の行動範囲を狭めています。
地域内の事業者間で連携し、観光地を巡る周遊バスを共同で運行したり、交通機関の情報を多言語で分かりやすく発信したりといった取り組みが求められます。
人手不足
宿泊業や飲食業、小売業など、インバウンド需要の受け皿となる産業において、深刻な人手不足が大きな課題となっています。
特に、外国語に対応できる人材の確保は急務です。
これに対し、セルフレジや注文用タブレットの導入による省人化や、外国人留学生や在留外国人を積極的に雇用し、その語学力や文化理解力を活かすといった対策が必要です。
インバウンド市場で売れる商品開発には多角的なアプローチが求められる
拡大を続けるインバウンド市場で選ばれる商品を開発するためのポイントについて、市場のトレンド分析から、具体的な商品開発のヒント、そして事業者が向き合うべき社会課題まで、多角的に解説しました。
これからのインバウンド戦略で成功を収めるために必要なのは、もはや小手先のテクニックではありません。
日本の文化や技術、おもてなしの心といった、私たちが持つ真の価値と真摯に向き合い、それを世界中の人々が共感できる「物語」として商品に昇華させていく。
そんな、深く、そして誠実なアプローチが求められているのです。
ぜひ一度、東京トレジャーズにご相談ください。
まだ世界に知られていない日本の優れた伝統工芸品や、物語のある特別な逸品を発掘し、大切な方への最高の贈り物としてご提案する、法人にも対応のギフトコンシェルジュサービスです。